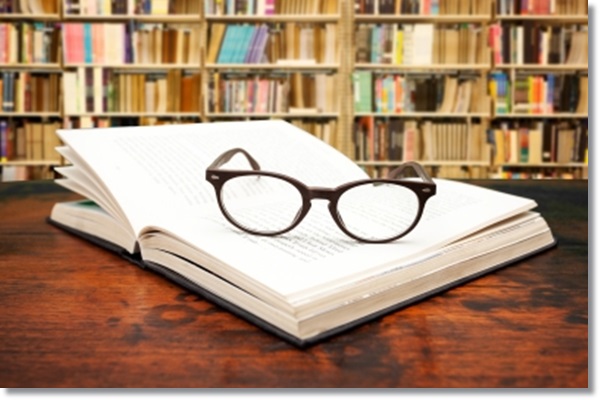フリーランスでお仕事をして収入を得た後には、翌年に確定申告を行う必要があります。
企業や団体で勤務している方にとっての年末調整が確定申告です。
中には還付金を受け取る方もいるかもしれません。
ここでは、フリーランスが知っておきたい税金に関する以下の項目をご紹介します。
この記事が役に立つ方
・フリーランスにて納税義務を持つ方
・フリーランスの税金について知りたい方
・節税対策に興味を持っている方
フリーランスが支払う税金の種類
フリーランスで働く方が納める税金として、次の6種類があげられます。
・所得税
・住民税
・消費税
・国民健康保険料
・国民年金
・個人事業税
所得税
所得税は前年度の「所得」に対して課せられる税金(国税)です。
所得は「収入(売上)-(経費+控除額)」にて算出されます。
仮に年収1,000万円の方で「経費」が500万円、「控除額」が200万円の場合、1,000万円-(500万円+200万円)=「300万円」が年間所得(課税所得金額)です。
|
課税所得金額 |
税率 |
課税控除額 |
|
1,000円から1,949,000円 |
5% |
0円 |
|
1,950,000円から3,299,000円 |
10% |
97,500円 |
|
3,300,000円から6,949,000円 |
20% |
427,500円 |
|
6,950,000円から8,999,000円 |
23% |
636,000円 |
|
9,000,000円から17,999,000円 |
33% |
1,536,000円 |
|
18,000,000円から39,999,000円 |
40% |
2,796,000円 |
|
40,000,000円以上 |
45% |
4,796,000円 |
参考資料
国税庁「所得税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
先述した300万円の年間所得(課税所得金額)の所得税は、300万円×10%(所得税率)-97,500円(課税控除額)=202,500円です。
所得税は、毎年2月16日~3月15日の確定申告の期間内に納めることが義務付けられています。
※確定申告の期間は暦などで変動あり
所得税の還付金
収入(売上)からすでに源泉徴収済みの所得税が、確定申告後の所得税よりも多かった場合に限り、指定した金融機関口座に「還付金」として後日入金されます。
一応記しておきますが、還付金はATMの操作では受け取ることができません。
あくまでも確定申告を行った方”のみ”が還付金の受け取り対象です。
住民税
住民税は居住している市区町村と都道府県に対して納める税金(地方税)です。
前年度の所得を基に算出した住民税を、翌年の6月以降に支払うことになります。
そのため所得税の確定申告を行った方であれば、住民税の確定申告は不要です。
住民税は「前年度の所得×10%(所得割)+5,000円(均等割)」にて算定します。
前述の300万円の年間所得(課税所得金額)の場合、300万円×10%+5,000円=「305,000円」が住民税額として請求される形です。
住民税は1回で全額納付するか、4回の分納のいずれかとなります。
分納の場合には、6月と8月と10月と翌年の1月の末日が納付期限です。
消費税
消費税は所得税の確定申告を行った「2年前」の年間課税売上金額が、1,000万円を超えた方に納付義務が生じる税金(国税)です。
コンビニやスーパーなどのショッピング時に納めるものではありません。
あくまでも消費税の課税事業者が、その年に預かった消費税額を翌年の3月31日までに納めるものです。
※確定申告の期間は暦などで変動あり
国民健康保険料
フリーランスの方が、おおむね加入するのが国民健康保険です。
(社会保険の任意継続や、家族の扶養に入る方は除外されます)
国民健康保険の加入を継続するためには、国民健康保険料を納めることが必須です。
国民健康保険料は、前年度の所得と加入者数、そして年齢によって算出されます。
お住いの自治体(市区町村)ごとに金額が異なるため、詳しくは市区町村の公式サイトを参照してください。
国民健康保険料は、確定申告後の6月から翌年の3月にかけて月々支払うことになります。
※年間保険料の一括払いも可能です
納めた分の国民健康保険料は、その年の所得控除(社会保険料控除)として計上できます。
国民年金
フリーランスで働く20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することになります。
(第1号被保険者)
国民年金はその年度ごとに定められた年金保険料を月々納める形です。
※2022年度は16,590円/月
国民年金は6ヶ月分や1年分、2年分の「前納制度」も設けられています。
※2年前納に限り月々の納付と比べて支払総額が割引される
ちなみに国民年金も所得控除(社会保険料控除)の対象です。
個人事業税
年間所得金額が290万円を超えたフリーランスの方は、個人事業税をお住まいの都道府県に納めることになります。
個人事業税は業種ごとに税率が異なる(3%から5%)のが特徴です。
確定申告後の8月と11月の2回に分けて納付します。
フリーランスの節税対策
フリーランスの節税対策は、経費の計上と所得控除額がカギとなります。
多くの経費を計上し、所得控除額を増やすことで所得税を抑えることが可能です。
※所得=収入(売上)-(経費+控除額)
ただし計上できる経費には限度があります。
その点を踏まえた上で、レシートや領収書を受け取るようにしましょう。
※スマホのカメラで撮影した領収書やレシートの画像も対象です
国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
フリーランスの節税~経費にできる税金
フリーランスが納める税金の中には、経費(租税公課)として計上できるものも含まれています。
・個人事業税
・消費税
・固定資産税
・不動産取得税
・印紙税
・登録免許税
・自動車税、軽自動車税
個人事業税
個人事業税は経費(租税公課)として「全額」計上できます。
「事業を継続する際に必要な費用」として認められていることがその理由です。
消費税
消費税は「税込経理」を採用した場合に限り、経費(租税公課)として認められます。
「税込経理」とは、仕入金額や売上に対して消費税込みの金額を計上する会計処理です。
固定資産税
事業用の不動産(土地や建物)への固定資産税も経費(租税公課)に含まれます。
自社ビルや所有する店舗やオフィスが対象です。
フリーランスの方は、持ち家(戸建住宅やマンションなど)の固定資産税の「按分」が適用されます。
たとえば事業用で使っている面積が総床面積の30%の場合、納めた固定資産税の30%分を経費として計上する形です。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を購入した際に課せられる税金(都道府県税)です。
不動産取得税は事業用の不動産を購入した際に、経費(租税公課)の対象となります。
自宅の場合、事業に使用している部分のみ「按分」扱いでの経費計上が可能です。
印紙税
印紙税は契約書などに貼付(ちょうふ)する収入印紙に対する税金です。
印紙税も事業に必要な費用として認められているため、経費(租税公課)に含めることができます。
印紙税は収入印紙を購入した時点で納付完了です。
申告の必要はありません。
登録免許税
登録免許税は法人(株式会社など)や不動産の登記を行った際に、所轄の法務局に納める税金です。
業務で使用する自動車や船舶、航空機も登録免許税の対象となるケースがあります。
特許権の申請手続きなども登録免許税の納付対象です。
※特許権の登録免許税の納付先は特許庁
登録免許税も経費(租税公課)として計上ができます。
自動車税、軽自動車税
自動車税は都道府県税、軽自動車税は市区町村税です。
事業で使用している自動車であれば、自動車税や軽自動車税も経費(租税公課)扱いとなります。
自家用と兼ねている自動車に関しては、事業用の割合のみ経費の計上が可能です。
フリーランスの節税~所得控除
フリーランスの節税対策には所得控除も含まれます。
所得控除は定められた条件をクリアすることで適用される税金の優遇措置です。
主な所得控除には次の種類があります。
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・寡婦(夫)控除(ひとり親控除)
・勤労学生控除
・配当控除
・住宅借入金等特別控除
基礎控除
基礎控除は、確定申告や年末調整を行う方すべてに適用される控除です。
|
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
~24,000,000円 |
480,000円 |
|
24,000,001円~24,500,000円 |
320,000円 |
|
24,500,001円~25,000,000円 |
160,000円 |
|
25,000,001円~ |
0円 |
青色申告承認申請を所轄の税務署に提出済みの方には、青色申告特別控除が別途適用されます。
※最大65万円の青色申告特別控除の場合、650,000円+480,000円=1,130,000円
配偶者控除
確定申告を行うフリーランスなどの方に配偶者が存在する場合、配偶者控除の対象となるケースがあります。
※生計をともにする配偶者の年間所得が48万円以下
|
配偶者控除を受ける方の年収 |
一般控除 |
老人控除 |
|
~9,000,000円 |
380,000円 |
480,000円 |
|
9,000,000円超~9,500,000円 |
260,000円 |
320,000円 |
|
9,500,000円超~10,000,000円 |
130,000円 |
160,000円 |
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者控除の対象外となった場合に適用される優遇措置です。
最大で38万円の控除が受けられます。
配偶者特別控除の主な条件は次のとおりです。
・配偶者特別控除を受ける方の年収が1千万円以下
・配偶者の年間所得が48万円超から133万円以下
・生計をともにする配偶者特別控除を適用していない配偶者
扶養控除
生計をともにする16歳以上の扶養家族(年間所得48万円以下)を持つ方への控除です。
|
|
扶養控除額 |
|
控除対象扶養親族(一般) |
380,000円 |
|
特定扶養親族 |
630,000円 |
|
老人扶養親族 |
480,000円 |
|
老人扶養親族 |
580,000円 |
雑損控除
盗難や災害、横領による資産の損害に対する所得控除の種類です。
以下のいずれかのうち、多い方の金額が雑損控除として認められます。
・(損害金額+災害など関連支出金額-保険金などの額)-総所得金額など×10%
・(災害関連支出金額-保険金などの額)-50,000円
医療費控除
年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費に対する控除です。
納税者本人および生計をともにする家族の医療費が対象となります。
医療費控除の計算式は以下のとおりです。
(支払い済みの医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-100,000円
※年間総所得金額などが200万円未満の方は、総所得金額など×5%
社会保険料控除
フリーランスの方の場合、その年に納めた国民健康保険料や国民年金が社会保険料控除に該当します。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)などへの加入者が対象となる控除です。
年間で支払った掛金の全額が控除として認められます。
生命保険料控除
その年に支払った生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料に対する優遇措置です。
2012年1月1日以降の保険契約の場合、次の控除額が適用されます。
|
年間支払保険料など |
所得控除額 |
|
20,000円以下 |
年間支払保険料などの全額分 |
|
20,000円超から40,000円以下 |
支払保険料など×50%+10,000円 |
|
40,000円超から80,000円以下 |
支払保険料など×25%+20,000円 |
|
80,000円超 |
40,000円 |
地震保険料控除
2006年12月31日までに契約済みの損害保険料(地震など損壊部分)への控除です。
|
年間支払保険料など |
所得控除額 |
|
地震保険料 |
地震保険料の全額分 |
|
地震保険料 |
50,000円 |
|
旧長期損害保険料 |
旧長期損害保険料の全額分 |
|
旧長期損害保険料 |
支払保険料×50%+5,000円 |
|
旧長期損害保険料 |
15,000円 |
|
地震保険料+旧長期損害保険料 |
それぞれの年間支払保険料ごとに |
寄附金控除
納税者本人が国や地方公共団体などに寄付をした際に受けられる優遇措置です。
次のいずれかのうち低い方の金額が寄付金控除として認められます。
・年間で支払った特定寄附金の合計金額-2,000円=寄付金控除
・年間総所得金額など×40%-2,000円=寄付金控除
ちなみに「ふるさと納税」も寄付金控除に含まれます。
「ふるさと納税額-2,000円=寄付金控除額」
障害者控除
納税者本人や配偶者や扶養家族が、障害認定(所得税法)されている場合に適用される控除です。
|
|
所得控除額 |
|
障害者 |
270,000円 |
|
特別障害者 |
400,000円 |
|
同居特別障害者 |
750,000円 |
寡婦(夫)控除
年間総所得500万円以下の寡婦に対する270,000円の所得控除です。
寡夫控除は2020年より「ひとり親控除」に名称が変更され、控除額も350,000円に増加しています。
勤労学生控除
高校や大学、高専や専門学校に通いながら働く方が受けられる優遇措置です。
・合計所得金額が75万円以下
・給与所得などの所得が10万円以下
学校に通いながらフリーランスとして仕事をしている方で、上記の条件を満たした場合には270,000円の所得控除額が適用されます。
配当控除
日本国内株式などの配当所得にて、総合課税を選んだ方が対象となる控除です。
外国法人からの配当所得は対象外となります。
住宅借入金等特別控除
いわゆる「住宅ローン減税」と呼ばれている所得税の優遇措置です。
住宅借入金等特別控除の主な条件は次のとおり。
・2021年9月30日までに居住用注文住宅の新築契約を果たした方
・2021年11月30日までに居住用中古住宅や分譲住宅、増改築などの契約を済ませた方
・年間合計所得3,000万円以下の方
あくまでも「住宅ローンの契約者本人が居住する」ことが条件のため、不動産投資物件には適用されません。
フリーランスの税金は会社員よりも高いのか?
フリーランスへの転身後、企業や団体に勤務する方よりも納める税金が高くなるとは限りません。
|
|
納める税金などの種類 |
|
フリーランス、個人事業主 |
・所得税 |
|
企業や団体に勤務する方 |
・所得税 |
給与所得控除
企業や団体に勤務する方には、給与所得控除が適用されます。
とはいえ、自身で確定申告を行う方以外は「年末調整」にて処理されるため、あまりピンとこないかもしれません。
|
給与などの収入金額 |
給与所得控除額 |
|
1,625,000円まで |
550,000円 |
|
1,625,001円から1,800,000円まで |
収入金額×40%-100,000円 |
|
1,800,001円から3,600,000円まで |
収入金額×30%+80,000円 |
|
3,600,001円から6,600,000円まで |
収入金額×20%+440,000円 |
|
6,600,001円から8,500,000円まで |
収入金額×10%+1,100,000円 |
|
8,500,001円以上 |
1,950,000円 |
たとえば500万円の年間給与収入の場合、5,000,000円×30%+80,000円=1,580,000円の給与所得控除額が適用されます。
※5,000,000円-1,580,000円(給与所得控除額)=3,420,000円(給与所得)
給与所得より、社会保険料控除や基礎控除(480,000円)などを差し引いた金額が「課税所得金額」となります。
フリーランスは経費と控除額で税金が割安になる可能性
一方、フリーランスの所得は、「収入-(経費+控除額)」で算出されます。
同じく500万円の収入で経費と控除額の合計が300万円の場合、500万円-300万円=200万円の課税所得金額です。
ただし青色申告特別控除(65万円)が適用された際には、2,000,000円-480,000円(基礎控除額)-650,000円(青色申告特別控除)=「870,000円」の課税所得金額となります。
経費の金額にもよりますが、青色申告を選択することで、フリーランスが納める税金が割安になる可能性を秘めているのは確かです。
まとめ
ここまで、フリーランスが知っておきたい税金に関する以下の項目を紹介してきました。
・フリーランスが支払う税金の種類
・フリーランスの節税対策
・フリーランスの節税~経費にできる税金
・フリーランスの節税~所得控除
・フリーランスの税金は会社員よりも高いのか?
フリーランスは、経費の計上や控除額の適用による節税対策が可能です。
確定申告をスムーズに済ませるためにも、市販の会計ソフトなどを上手に活用することをおすすめします。
当記事がフリーランスで働く方にとって、税金の基礎知識の入口となれば幸いです。